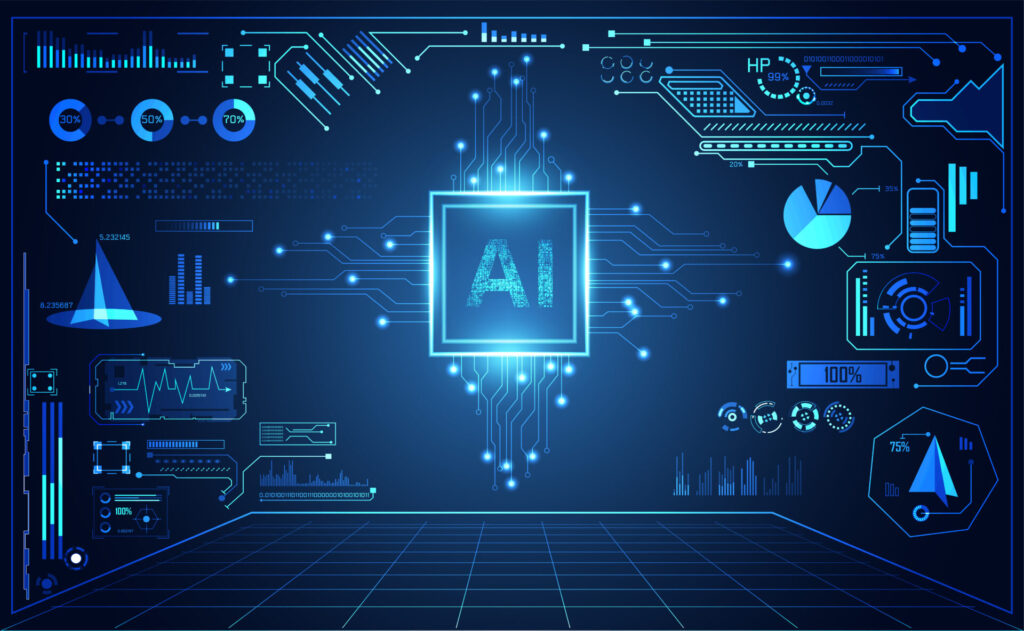COLUMN
#土木の未来を考える

建設業界の未来はどうなる?人材不足と技術革新から見る今後の展望
2025.6.17
目次
街の風景をよく見てみると、あちこちでクレーンが動き、作業着姿の人たちが忙しそうに働いているのを目にします。
かつては「日本の高度成長を支えた産業」として華やかに語られた建設業界。
今後に目を向けると、ある深刻な課題が浮かび上がってきます。それが「人材不足」です。
建設業界の現場で今、「人材不足だ」「今後、職人がいなくなるかもしれない」といった切実な声が聞こえてきます。
ベテランの職人さんたちが次々と現場を離れ、若い世代はなかなか入ってこない。
建設業界はまさに大きな人材不足という課題を抱えた転換期を迎えています。
一方で、AIやロボットといった最先端技術が次々と導入されはじめていて、「これまでの建設業界」とはまるで違う景色が見えはじめています。
今回は、建設業界の人材不足等の課題と今後の展望を通して、建設業界のこれからをみていきましょう。

建設業界を取り巻く現状と今後の課題
建設業界での人材不足が深刻化する現在
建設業では、人材不足が今後の大きな課題となっています。
少子高齢化が進む日本社会全体の流れの中で、この建設業界も例外ではありません。むしろ、その影響を最も早く、最も深刻に受けている分野の一つと言っても過言ではないでしょう。
2023年度の国土交通省が発表した統計によると、建設業界に従事する方のうち、55歳以上が全体35%を占めていることが分かりました。これに対して、29歳以下の若手人材はわずか12%。この年齢分布の歪みが意味するところは非常に大きく、まさに「担い手がいない業界」「人材不足」になりつつある現実を浮き彫りにしています。
さらに驚くべきは、その就業者数の推移です。
平成9年(1997年)には685万人だった建設業界就業者が、令和3年(2021年)には483万人まで減少。四半世紀で約200万人もの労働力がこの業界から姿を消したことになります。これほどの規模で人が減っているのに、社会インフラの需要は止まることを知りません。道路、橋梁、上下水道、学校、病院、住宅…。生活に必要なあらゆる基盤を支える仕事が、今まさに人材不足という根本的な課題に直面しているのです。
では、なぜ若者が建設業界を選ばないのか。人材不足といわれているのか。
その理由は一つではありませんが、よく指摘されるのが「就業環境」「労働条件」「業界イメージ」の3つです。
建設業界における人材不足は全国的な問題ですが、その内容は地域によって大きく異なります。
特に都市部では求人の競争が激しく、待遇や働き方の柔軟性で他業種に後れを取っている現実があります。地方ではまた別の問題が浮かびあがってきますそれは、「そもそも人がいない」という課題です。
過疎化や高齢化が進んだ地域では、若者の多くが都市部へと流出してしまい、地元での採用活動すらままならない状況が続いています。その結果、工事の着工が遅れたり、必要な技術が地域に残せなかったりと、事業継続自体が危ぶまれるケースも少なくありません。
このように、「人がいない」という単純な表現の裏には、地域によって異なる複雑な要因が絡み合っているのが現状なのです。
就業環境とイメージのギャップ
「建設業界」と聞いて、真っ先にどんなイメージが浮かぶでしょうか?
おそらく多くの方が、「きつい」「汚い」「危険」──いわゆる“3K”という言葉を思い出すのではないでしょうか。このような印象が、人材不足に拍車をかけているのは間違いありません。
これはもう、建設業界に長く染みついたイメージです。しかも、全くの的外れというわけでもなく、実際の現場では、真夏の炎天下での作業や、重機の操作、高所での作業など、身体に負担がかかる場面も少なくありません。だからこそ、「大変そう」という印象が広く浸透してしまっているのでしょう。
でも、それって本当に“今の建設業界”を表しているのでしょうか?
ここ数年で、建設業界の現場の姿は大きく変わりつつあります。たとえば、昔は図面といえば紙の束だったのが、今や現場監督はタブレット片手に現場を回っています。工程の進捗も、クラウドでリアルタイムに管理され、関係者間で瞬時に情報共有が可能です。ドローンで上空から測量を行ったり、BIMという3Dモデルを使って建物を設計したり──まさに“スマート建設”と呼ばれる時代に突入しているのです。こうした変化は今後さらに加速していくと考えられ、デジタルに強い若者にとっても活躍のチャンスは大いにあります。
とはいえ、こうした現代的な取り組みが社会全体に知られているかというと、残念ながらその浸透度はまだまだ。就活中の学生たちに話を聞くと、「泥まみれの現場で汗を流す」イメージが強く残っていて、そこから抜け出せていない印象があります。「建設=厳しい、つらい、大変」といったステレオタイプな印象が、志望動機の障壁になっているのは否定できません。
実際のところ、建設業の仕事というのは“現場で汗をかくだけ”ではないのです。たとえば施工管理の職種では、パソコンの前で工程表とにらめっこしながらスケジュールを組んだり、資材や人員の調整をしたり、クライアントや職人さんとの打ち合わせに奔走したり…。現場に出ている時間よりも、頭をフル回転させている時間のほうが長いかもしれません。
この仕事で求められるのは、体力以上に“段取り力”だったり、“調整力”だったりします。突発的なトラブルにどう対応するか、どこまで先を見通して準備を進められるか──その判断がプロジェクト全体の進行に大きく影響するのです。ある意味、現場という「生きもの」をマネジメントする仕事、と言ってもいいかもしれません。
なのに、そのリアルな姿が、世間にはまだあまり届いていない。スマートな部分、知的な部分、誇れる部分がたくさんあるにもかかわらず、外からは見えにくいのです。それどころか、昔のイメージばかりが先行してしまって、結果的に若い人の参入を妨げてしまっている──これは、今後のことを考えるとちょっともったいない話ですよね。
建設業が抱える「人材不足」という課題は、もしかしたら、業務内容そのものの問題というより、「本当の姿が伝わっていない」ことの方が根本にあるのかもしれません。地道だけど、伝え方を変えていくこと。そうすることで、業界全体のイメージが少しずつでも、確実に変わっていき、人材不足という課題にいい影響を与えていくのではないでしょうか。
地方と都市で異なる課題とチャンス
先述の通り、建設業界が抱える課題は、地域によって大きく異なります。都市部では再開発や大規模インフラ整備が相次ぎ、常に高い施工需要が存在しています。その一方で、人材の確保は容易ではなく、同業他社との獲得競争が激化しています。工期短縮のプレッシャーや施工の高度化により、現場は慢性的な人材不足に悩まされています。
一方、地方の現場ではまた別の課題があります。働き手の確保が年々困難になっており、特に若年層の採用が難しくなっています。若年層の都市部流出により、地元での採用は年々難しくなっています。ただし、地方には防災インフラや老朽設備の更新など、地域に根差した需要が確実に存在しています。また、住居費の安さや自然環境の豊かさを生かし、テレワークや遠隔施工支援などの技術を導入すれば、新しい働き方を実現できる可能性も広がります。
都市と地方、それぞれの課題と特性を正しく理解し、柔軟に人材や技術を配置することが、今後の建設業の持続性を支える、人材不足の課題を解消するカギとなるでしょう。
建設業界の人材不足解決に向けて進められている対策
時間外労働の是正と働き方の見直し
2024年から建設業にも適用された時間外労働の上限規制は、大きな転機となりました。
従来の長時間労働が制限されることで、企業は就業時間内で成果を出す体制づくりを迫られています。そのためには、業務の棚卸しとタスクの最適化、役割分担の見直しが必要です。
また、現場では交代制の導入や工程ごとの時差出勤、リモートで対応可能な業務の内勤化など、柔軟な働き方が模索されています。時間に追われる働き方から脱却することは、離職率の低下にも直結します。
今も今後も、人を大切にする現場づくりが、結果として持続可能な建設業・人材不足解消の基盤となるのです。
適切な工期設定と受発注の見直し
働き方改革を本気で進めようとすれば、避けて通れないのが「工期の問題」です。
これまでの建設業界では、「早く、安く」という風潮が強く、短納期での工事や“突貫”と呼ばれる無理な進め方が半ば当たり前になってきました。その結果、現場の職人さんたちは慢性的な残業に追われ、疲弊する日々が続いていたのです。
こうした状況を改善するため、国は公共工事において週休2日制の試行や、適正工期の確保に向けたガイドラインの整備を進めています。では、実際にどうやって工期を見直すのか。その一例として、発注者と受注者が協力して工程を見直す「フロントローディング」の導入も注目されています。これにより、今後は無理のない計画と効率的な施工が可能になるでしょう。適正な工期は品質の向上にもつながるため、業界全体での意識改革が求められているのです。
今後の建設業界を支えるカギ:「人」と「技術」
外国人労働者・女性・シニアなど多様な人材の活用
「人材不足なら、他の力を借りればいいじゃないか」と、最近ではそんな声も増えてきました。
たとえば外国人労働者。
技能実習制度から「特定技能」へと制度が見直され、東南アジアなどから多くの若者たちが日本の建設現場にやって来ています。言葉や文化の違いは確かにありますが、彼らの勤勉さや吸収の早さは現場でも評価されており、今や欠かせない戦力です。
今後は語学支援や生活サポートなど、長期定着に向けたフォロー体制の構築が重要です。
また、女性の進出も見逃せません。かつては「男の世界」と言われてきた建設業界ですが、近年は女性の施工管理者や技術者も少しずつ増えてきました。技術者や現場監督の活躍も少しずつ広がりを見せています。例えば、女性専用の更衣室やトイレ設置、育児支援制度などを整える企業も増えつつあり、今後を見通した多様な働き方の受け入れが進んでいます。
さらに、定年退職後のベテランを再雇用し、若手への技術継承や指導役として活用する事例も見られます。
長年培ってきた経験や技術は、一朝一夕で身につくものではありません。高齢になっても「もう少し現場に関わりたい」という人たちの知恵や視点を、いかに活かすか。そこに、建設業界の底力がある気がします。
今後、100年時代において、年齢に縛られない人材活用の柔軟性が問われています。
技術革新による省力化と生産性の向上
現場の変化は、人材だけではありません。テクノロジーの進化が、今後の建設業界に新しい風を吹き込んでいます。
ICTやBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)、ドローン、ロボットなどの導入が進み、施工現場の効率化・省力化が現実になりつつあります。特にスマートコンストラクションの導入により、測量から設計・施工・管理までの一元化が可能となり、人的負担を大幅に軽減しています。
AIの活用も進み、工事の進捗管理や施工計画の自動最適化、さらにはインフラ点検などへの応用が始まっています。これらの技術は、今後の人材不足という構造的課題に対する打開策となるでしょう。
技能継承と教育の新たなかたち
職人の技をどう次世代に伝えるか
「昔は、先輩の背中を見て覚えたもんだよ」。そう語る職人の言葉には、ある種の誇りと懐かしさがにじみます。
けれど、今はどうでしょう。現場の流れはスピード重視、少人数化も進み、「教える余裕」がどんどん失われているのが実情です。新人がじっくり学ぶ環境がないまま、技術やノウハウが現場とともに消えていく……。そんな“技術の空白”が、じわじわと広がっているのです。
いくらテクノロジーが進んでも、最後の仕上げは“人の手”にかかっている場面がまだまだ多いです。だからこそ、今こそ技術継承の仕組みが必要なのです。
学び方のアップデート:VR・ARで“体験する”教育へ
従来の徒弟制度的な教育だけでは、どうにも追いつかない。そんな時代に登場したのが、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使った次世代の教育手法です。
たとえば、橋梁の溶接や高所作業の手順を、リアルな3D映像で何度でも繰り返し練習できる。失敗してもケガはしないし、納得いくまで試せる。そんな「安心して失敗できる場」が、新人育成の強い味方になってくれています。
また、現場の映像を記録し、後輩に“疑似体験”させるようなリモート教育も広がっています。これなら、ベテランの“目のつけどころ”や“ちょっとしたコツ”も、形にして残すことができる。技術を言葉と映像で今後に残していく、そんな動きが始まっているのです。
高専・専門学校・大学との連携
高等教育機関と企業の連携も進められています。インターンシップ制度や企業が授業に参画する取り組みは、学生にとって実践的な学びの機会となります。
実際の現場に触れた学生が「将来は建設業に進みたい」と言ってくれる瞬間は、建設業界全体にとって希望の灯でもあります。
また、国土交通省の後押しもあり、土木・建設分野に特化したカリキュラムの整備が進んでいます。教育と現場を結ぶ橋渡しの強化が、今後の担い手育成に欠かせません。
建設業界の今後を描く:持続可能な社会に向けて
“作る”から“守る”へ:インフラ老朽化という新たな戦場
かつては「どんどん新しいものを作る時代」だった建設業も、今後は「いかに長持ちさせるか」「どう維持管理するか」が中心になってくるでしょう。
たとえば、高度経済成長期に建てられた橋や道路、トンネルの多くが、いまや老朽化の時期を迎えています。それらを放置してしまえば、事故や機能不全を引き起こすリスクは計り知れません。
だからこそ、今後の建設業界は、「新設」だけでなく「メンテナンス」という視点が欠かせません。点検・診断・補修といった仕事に携わる人材の重要性が、ぐっと高まってきているのです。
点検にドローンを活用したり、ひび割れをAIで自動検出するなど、こちらも技術の活用が鍵を握ります。
カーボンニュートラル・脱炭素と建設業の役割
近年、どの業界でも「環境配慮」がテーマになっていますが、建設業界も例外ではありません。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、建設業界にも環境配慮の視点が求められています。むしろ、建設資材や機械はエネルギーを大量に使うため、地球環境との関係性は非常に深いです。
そんな中で注目されているのが、「グリーンインフラ」や「低炭素建材」です。たとえば、CO2排出を抑えたコンクリートや、再生可能な木材を活用した建物。あるいは、断熱性の高い素材を使って冷暖房のエネルギーを抑えるような工夫も広がっています。
建設の技術が、地球にやさしくあるために進化していく。その流れは今後さらに加速するでしょう。
世界の建設業界から学ぶヒント
日本の建設業が抱える課題は、実は世界各国でも共通しています。人材不足、高齢化、環境への配慮、そして技術革新への対応——。こうした問題に対し、海外では先進的な取り組みが始まっています。
例えば北欧諸国では、建設現場における完全週休2日制の徹底と、ワークライフバランスを重視した働き方が浸透しています。また、英国ではBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の義務化が進み、設計から施工、維持管理までの効率化と品質向上が図られています。さらにシンガポールでは、外国人労働者の活用と同時に、自動化の導入が進み、省力化と施工スピードの両立が実現しています。
こうした事例から学べるのは、「制度と技術の両輪による変革」です。日本でも、自国の文化や現場特性を踏まえつつ、海外の知見を柔軟に取り入れることが、今後の持続可能な建設業につながっていくでしょう。
企業・行政・教育機関の三位一体で進む業界変革
企業側の取り組み:働きやすい職場づくり
「人材不足だ」と嘆くだけでは、何も変わりません。そこで今、多くの建設企業が「魅力ある職場づくり」に力を入れ始めています。
たとえば、デジタルツールを使った業務の効率化。施工管理アプリで現場の進捗を可視化したり、クラウドで図面を共有したり。これまで時間をかけていた作業がスムーズになれば、今後は残業も減り、ミスも減っていくでしょう。
また、福利厚生を見直したり、研修制度を充実させたりして、「この会社で働き続けたい」と思ってもらえる環境を整えていく。そうした取り組みが、少しずつ若い人材を引き寄せているのです。
「建設業界の仕事って、こんなにおもしろいんだ」――そんな声が現場から自然と出てくる未来が、今後きっとやって来ると信じています。
行政の支援策と制度整備
もちろん、企業だけで変えられることには限りがあります。そこで頼りになるのが、行政や教育機関との連携です。
たとえば、国が進める「建設キャリアアップシステム(CCUS)」では、職人の資格や実績を“見える化”することで、スキルに応じた処遇改善を後押ししています。これは職人の誇りを支える、大きな仕組みです。
まとめ:建設業界の「今後」をどう描くか
今、建設業界は「危機」と「変革」の分岐点に立っています。人材不足や老朽化インフラなど厳しい課題がある一方で、技術革新や多様な人材の活用といった新しい道も切り開かれてきています。
建設業界の人材不足は、一朝一夕で解決する問題ではありません。しかし、就業イメージの刷新、柔軟な働き方の導入、若年層への積極的な情報発信など、小さな改革を積み重ねていくことで、今後に希望をつなぐことは可能です。
建設業界はこれからの日本社会にとって、今後ますます重要な役割を担います。人材不足という壁に立ち向かいながら、今後の新たな可能性を切り開く時が、いままさに訪れているのです。
SSFホールディングスの能力開発校ADSでは、次世代の土木技術者を育成します。現場で活躍できる人材の輩出を通じて、業界全体の発展に貢献いたします。 職場見学も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。