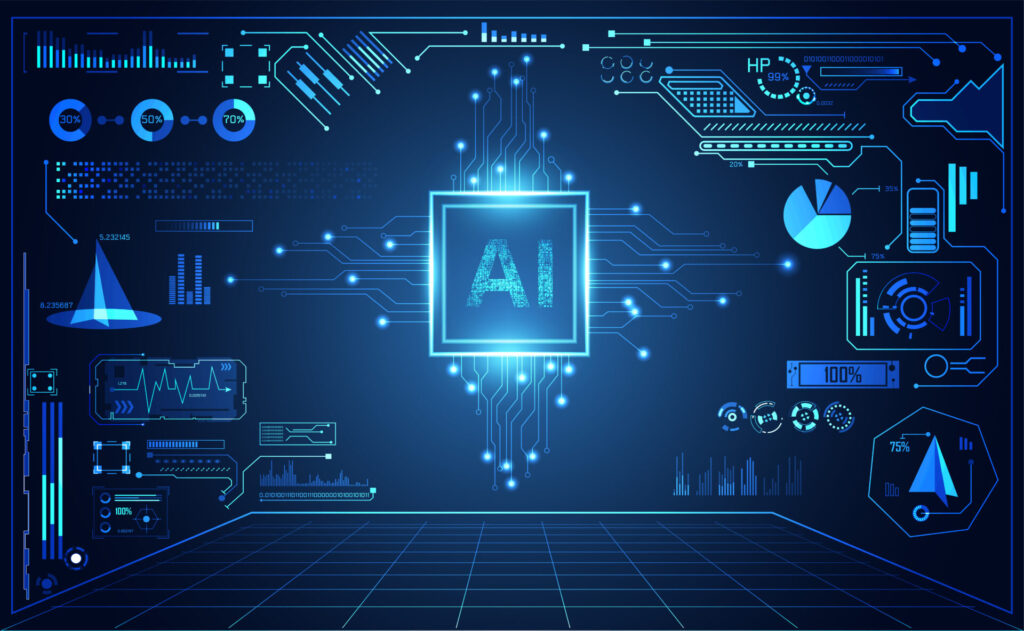COLUMN
#土木の未来を考える

外国人材は建設業界を救うのか?国際協力と人材戦略の未来
2025.7.9
建設業界は深刻な人材不足に直面しています。高齢化や若手の減少が進むなか、外国人材への期待が高まりつつあります。しかし、単に外国人材を「労働力」として受け入れるだけでは、課題の解決にはなりません。
本コラムでは、外国人材が建設業界でどのような役割を果たし、どのように未来を支える存在となり得るのかを探ります。国際協力や制度の仕組み、建設業の現場での実態、そして新しい人材戦略のあり方まで、多角的に考えていきましょう。

建設業界を襲う人材不足という現実
高齢化と若年層の建設離れ
建設業界では、今、かつてないほどの人材不足が深刻化しています。その背景にあるのは、長年指摘されてきた高齢化の進行と、若年層の建設離れです。建設業全体で、若い世代の就業意欲が減退し、人手の確保が年々難しくなっています。
かつては「手に職を」と志した若者たちも、今ではITやサービス業などへ流れていく傾向が強く、建設業における人材不足は、ますます加速しています。
国土交通省の統計によると、建設業従事者の約3割が55歳以上。つまり10年後には、大量の引退者によって人材不足のピークを迎えると予想されています。その一方で、29歳以下の若手の割合は全体のわずか1割程度。世代交代がうまく進まないことで、建設現場の人材不足は恒常的な課題となっているのです。
拡大する人手不足の数値と実態
労働人口の減少に加え、公共インフラの老朽化対策、防災・減災に向けた整備、そして都市部での再開発など、建設業界には今も多くの案件が集中しています。つまり、「仕事はあるが人がいない」これは一時的な現象ではなく、慢性的な人材不足の現れです。
特に地方では、数社で1つの現場をなんとか回すというケースも多く、人材不足が建設業の運営に直接影響する場面が目立ちます。建設業の現場では工程の遅延やコスト増が発生し、結果として品質や安全性への懸念が高まっているのが現実です。
人材不足が招く品質・納期への影響
かつては経験豊富な職人たちが工事を支えていましたが、現在ではその数が大きく減り、人材不足が技術継承の壁となっています。その穴を埋めるべく、新人や経験の浅い作業員が短期間で現場に投入されることが増えました。
こうした状況では、施工品質や現場全体のバランス調整が難しく、人材不足による納期遅延や事故リスクが高まっています。
ここで注目されているのが、外国人材の存在です。建設業界の人材不足を補う戦力として、外国人が実質的な役割を担いつつあるのです。とはいえ、彼ら外国人に頼るだけでは根本的な人材戦略とは言えません。次章では、制度的な背景と外国人受け入れの現状について詳しく見ていきます。
外国人労働者の受け入れと制度の変遷
技能実習制度と特定技能制度の違い
日本の建設業界では、慢性的な人材不足に対応するため、外国人材の受け入れを制度的に拡大してきました。代表的なものとしては「技能実習制度」と「特定技能制度」があり、この2つは目的や仕組みに明確な違いがあります。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的にした制度で、日本の建設業現場で実務を経験しながら技術を習得するという建前になっています。ところが、実態としては即戦力としての労働力供給に依存している面があり、本来の趣旨と現場のニーズの間にギャップがあることが、建設業界の人材不足問題と合わせてしばしば指摘されてきました。
現在、建設業の人材不足を補うための仕組みとして注目されているのが「特定技能制度」です。これは2019年に導入された在留資格で、深刻な人手不足が続く業種を対象に、一定の日本語能力と業務技能を持つ外国人を正式な労働力として受け入れる仕組みとなっています。
建設業の分野では「特定技能1号」が適用されており、型枠施工、鉄筋施工、トンネル推進工、建設機械施工など、業種ごとに定められた分野で就労が可能です。就労期間は最長5年で、転職も条件付きで認められています。従来の技能実習制度に比べて、より現場ニーズに即した制度設計となっており、企業側にとっても導入しやすい仕組みが整えられています。
この制度は、単なる労働者ではなく「即戦力としての外国人材」を前提としており、試験合格が条件となるため、受け入れ側の現場でも戦力化が期待されています。現在では、特定技能で在留する外国人のうち、一定数が建設業分野に従事しており、建設業全体の人材不足対策の中核的な役割を担いつつあります。
外国人材に頼らざるを得ない背景とは?
外国人材が建設業界に不可欠な存在となってきたのは、単なる経済合理性の問題ではありません。高齢化、若者の業界離れ、さらには技術者層の退職など、複数の構造的要因が重なり、人材不足の常態化が避けられない状況に陥っているからです。
2020年以降、コロナ禍によって外国人技能実習生の来日が一時的に途絶えたとき、多くの建設業現場が「人が来ない」という事態に直面しました。この経験は、人材不足に依存する体質が、いかに現場の脆弱性を露呈させるかを強く印象づけました。
その結果、今や外国人材は“補助”ではなく、“必須戦力”とみなされています。そして、建設業における人材不足の恒常化は、こうした依存を加速させる一因にもなっています。
制度の限界と現場からの声
とはいえ、制度が完璧に機能しているとは言えません。たとえば技能実習制度では転職の自由がないため、労働環境に問題があっても外国人労働者が移動できないケースが見られます。これにより、人材不足がありながらも外国人材が活用されにくい場面も発生しているのです。
また、受け入れ側である企業も、外国人材の日本語教育や生活支援といった周辺サポートまで担う必要があり、それが制度利用のハードルとなっている現実もあります。建設業の人材不足という構造的課題の中で、制度と現場のギャップをどう埋めるかは今後の大きなテーマです。
近年では、第三者機関の定期的なモニタリングや、地方自治体が主導する生活支援体制の構築など、制度の質を底上げする取り組みも進みつつあります。とくに中小規模の建設業者にとっては、こうした外部支援の存在が外国人材の定着に直結する重要な要素となるでしょう。制度の柔軟性と現場支援の両立が、持続可能な外国人受け入れの鍵を握っています。
次章では、そうした制度の枠を超えて、実際に建設現場で働く外国人のリアルな姿や課題、そして現場での工夫を見ていきます。
建設現場で働く外国人たちのリアル
外国人材の現場での仕事ぶりと評価
建設業の現場では、外国人材が今や欠かせない戦力となっています。特に人手が集まりにくい型枠工事や解体作業などでは、外国人の存在が人材不足への対策として実質的な役割を担っているのが現実です。
「真面目で丁寧」「指示を素直に聞いてくれる」といった評価を受ける外国人労働者は多く、中には数年の実務経験を経て、現場リーダーを補佐する立場まで担う人もいます。建設業界の人材不足に直面する現場では、彼らの技術力と勤勉さが高く評価されており、日本人作業員との信頼関係も築かれています。
こうした状況を見れば、外国人が単なる“補助労働者”ではなく、“主力”の一端を担っていることがよく分かります。
言語・文化の壁とその対応策
とはいえ、人材不足を背景に外国人を急速に受け入れている現場では、言語の壁が大きな障害となることがあります。建設業の現場では、安全や品質に関わる細かい指示を正確に理解することが求められます。そのため、日本語の理解が不十分なまま現場に配属されると、事故や誤解が生まれるリスクが高まります。
これに対応するため、企業は通訳アプリや多言語対応の作業マニュアルを導入したり、視覚的な掲示物を整備したりと工夫を重ねています。また、研修時に日本語会話の基本を教えるプログラムを設けたり、作業工程をイラストで表現したマニュアルを導入することで、経験の浅い外国人労働者でも不安なく作業に入れるよう配慮する企業も増えています。人材不足のなかで外国人材を安全かつ円滑に活用するためには、こうした準備が不可欠です。
文化の違いにも注意が必要です。報連相の文化、上下関係の感覚、仕事に対する姿勢など、日本の職場文化とズレが生まれる場面は少なくありません。そのため、管理者側にも異文化理解やコミュニケーションの柔軟性が求められるようになってきています。
企業・現場が抱えるサポートの課題
外国人材を受け入れるということは、単に現場で作業させるだけでは終わりません。就労ビザ、住居、生活費、医療、緊急時対応など、日常のさまざまな支援も企業側に求められます。建設業における人材不足が長期化する中、外国人の“定着”をどう支えるかは新たな経営課題になりつつあります。
実際に、せっかく育てた外交人技能実習生が、サポート体制の不備から早期に帰国してしまうケースもあります。これは現場にとって大きな損失であり、人材不足がより深刻化する結果を招きかねません。
そこで、NPOや地域の多文化支援団体と連携しながら、外国人材の生活基盤づくりに力を入れる企業も増えています。今後の建設業が人材不足を乗り越えるには、現場と生活支援を一体化して考える視点が重要になってくるでしょう。
国際協力の視点で見る建設業の未来
発展途上国との人材交流の可能性
日本の建設業では、慢性的な人材不足に対する対策として、外国人材の受け入れにとどまらず、「人材育成」という観点を持った国際協力の形が注目されています。その一例が、発展途上国との双方向的な人材交流です。
たとえば、日本で実務を経験した外国人が、母国に戻って建設プロジェクトを主導する存在になるという流れが少しずつ広がっています。特にインフラ需要が高まっている東南アジア諸国では、日本の建設業が誇る技術や安全管理のノウハウは非常に高く評価されており、現地の人材育成にも貢献しています。
こうした交流は、建設業が抱える人材不足の一時的な解消にとどまらず、長期的な国際的信頼関係の構築につながる可能性を秘めています。
技術移転と相互利益のあり方
国際協力という視点で建設業を捉えると、「労働力の確保」だけでなく「技術の移転」も極めて重要な要素となります。日本の建設業界には、高い精度の測量技術、安全に対する徹底した管理意識、そして厳密な工程調整力といった強みがあります。
これらの技術を、外国人労働者に実務を通じて伝えていくことは、将来的にその人たちが母国の建設発展を支える力になるという意味でも重要です。言い換えれば、建設業の国際的な人材循環は、共に成長する土台となるのです。
また、日本の側にとっても、外国人材から新たな視点や働き方、デジタルリテラシーを学ぶ機会が生まれます。人材不足に悩む建設業だからこそ、多様な視点を取り入れる柔軟性が今、求められています。
アジアを中心とした建設分野の人材循環
今後の展望として注目されているのが、アジア諸国を中心とした「建設分野における人材循環ネットワーク」の形成です。ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーといった国々から多くの外国人が来日し、日本の建設現場で人材不足を支えている現状があります。
これを一過性の流れに終わらせず、研修制度や技能評価の整備、帰国後のキャリア設計支援などを含めた持続可能な循環モデルへと発展させていくことが望まれます。また、外国人材が日本国内で中堅職や管理職に就けるような環境づくりも、建設業全体の活性化と人材確保の鍵になるでしょう。
持続可能な人材戦略とは何か?
一時的な穴埋めではなく、共に成長する関係へ
建設業が抱える人材不足は、単なる一時的な現象ではなく、今や産業構造そのものに根差した慢性的な課題です。この問題に対して、外国人材の受け入れは一定の効果をもたらしていますが、それだけで十分とは言えません。
本当に必要なのは、「共に成長する」関係性です。外国人材を単なる穴埋め要員としてではなく、将来の管理職や専門技能者として育てることで、建設業の人材戦略が持続的なものへと変化します。
実際に、一部の企業では外国人向けのOJT制度、日本語研修、職種ごとのキャリア設計などを整備し、人材不足を乗り越えるための長期育成モデルを導入しはじめています。こうした取り組みは、建設現場の多様性と柔軟性を高め、業界全体の競争力にもつながります。
建設業の魅力をどう伝えるか
そもそも建設業界の人材不足は、業界そのもののイメージにも起因しています。長時間労働、危険な現場、報われにくい努力といった負の印象が、若者や外国人に敬遠される要因となっているのです。
この現状を打破するには、建設業の本当の魅力を伝える力が不可欠です。たとえば、地域の未来を形づくる使命感や、防災インフラの構築に携わる意義、ICTやロボティクスといった新技術との融合など、現代の建設は進化し続ける挑戦の場でもあります。
こうした情報を正しく発信し、「やってみたい」「関わってみたい」と思わせるアプローチが、新たな人材層の掘り起こしにつながります。
外国人も日本人も働きやすい建設現場づくり
人材不足を本質的に解決するには、「人が定着する現場づくり」こそが鍵です。外国人、日本人問わず、誰もが安心して働ける環境が整っていなければ、せっかく確保した人材も長くは続きません。
たとえば、多言語対応の安全教育、異文化理解を深める社内研修、意見交換の場づくりなど、外国人と共に働く意識を企業文化として根づかせることが必要です。こうした取り組みは、建設業全体の働き方改革にも直結します。
また、待遇や福利厚生の改善も不可欠です。特に中小企業では、「人を採るより辞められない環境づくり」が今後の課題です。これは外国人材に限った話ではなく、建設業の人材不足を根本から見直す試みとも言えるでしょう。
まとめ
人材不足という課題に直面する建設業界にとって、外国人材の存在はもはや欠かせないものとなっています。制度の枠組みを越えて、現場で汗を流し、技術を習得し、信頼を築いている外国人たちは、日本の建設を支える大切な仲間です。
しかし、本質的な課題は単なる人手の確保ではありません。建設業という分野がこれからも社会に必要とされ続けるためには、働く人一人ひとりが安心して成長できる環境づくりが欠かせません。外国人であっても、日本人であっても、やりがいや未来が見える現場こそが人を惹きつけ、定着を生み出します。
さらに、建設というフィールドは、国境を越えた連携が求められる時代に突入しています。発展途上国との協力や、技術移転を含めた国際的な人材循環は、単に日本を助けるだけでなく、世界の建設力を底上げする力にもなり得るのです。 建設業は“つくる”ことを通じて、人と社会をつなぐ産業です。その本質を見つめ直し、未来へとつなげるために、私たちは今、外国人材との共存と協働のあり方を改めて問い直す必要があります。小さな一歩の積み重ねが、建設業全体の大きな転換点につながっていくでしょう。
SSFホールディングスの能力開発校ADSでは、次世代の土木技術者を育成します。現場で活躍できる人材の輩出を通じて、業界全体の発展に貢献いたします。 職場見学も受け付けておりますので、初心者・未経験の方もぜひお気軽にお問い合わせください。